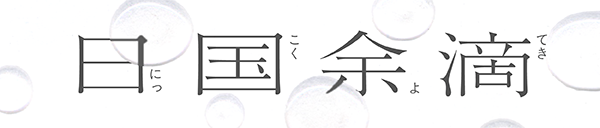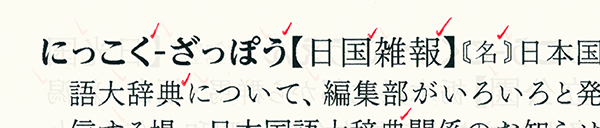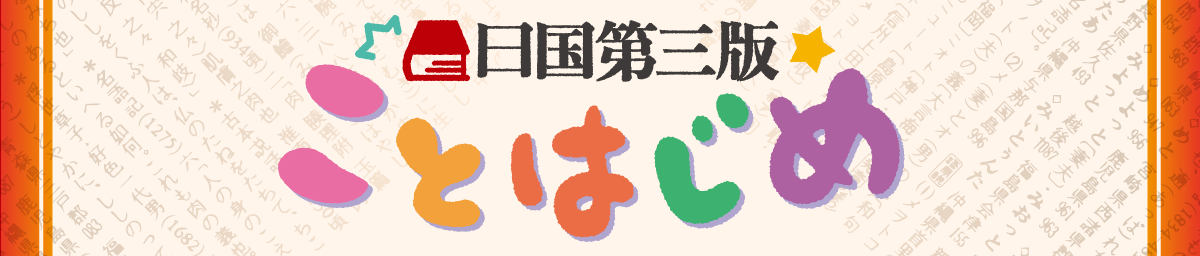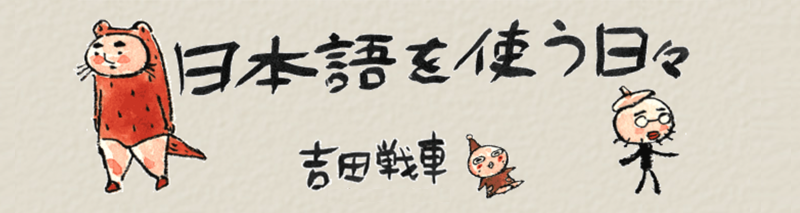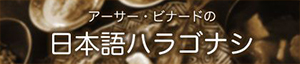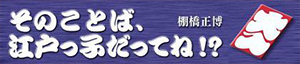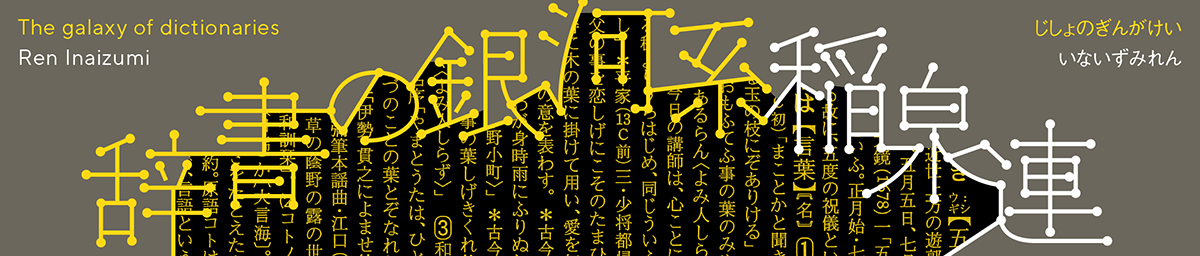
辞書の銀河系
第3回 前編
長い歴史の中で日本語はどのように変化し、どの時代にどのように使われてきたのか──。日本最大の国語辞典である『日本国語大辞典』は、「用例主義」に基づき、実際に使われた文例の形でその痕跡を積み重ねる言語の巨大な記録である。そして、この第三版の改訂作業において、辞書編集部全体を統括する室長を務めているのが、今回紹介する大野美和さんだ。
その日、小学館の辞書編集室を訪れた私は、彼女に「日国」の編集作業のリーダーを任されたときの気持ちを訊ねた。すると、大野さんの口からまず語られたのは少し意外な言葉だった。
「まさか、という思いでした」
彼女はそう言ってから、次のように続けたのだ。
「正直に言えば、最初に話が来たときは、『勘弁してもらえないかな……』っていう気持ちのほうが強かったんです。どう考えても大変な仕事だし、その時点ではまだ編集部にも坂倉さん一人しかいなかったですから」
大野さんが慎重にこう語った理由は、今から振り返ればよく分かる。これまで小学館の辞書編集部で長く辞書づくりに携わってきた彼女にとって、「日国」の改訂というプロジェクトはあまりに巨大なものであり、おいそれと立ち向かっていけるものではないことをよく知っていたからだ。
『日本国語大辞典』の第三版に求められることは、単なる「改訂」という言葉を超えた何かであるのは明らかだった。それに前版から約30年という歳月を経て、日本語や辞書出版を取り巻く環境も、研究手法も、社会のあり方も大きく変わっている。それら全てを踏まえた上で、日本語という言語の現在地を「用例」によって編み直す。それは時間も、人も、資金も、気の遠くなるほど必要な事業であった。
「人員はどうするのか、予算は十億円を超える規模になるけれど、事業が黒字になる見込みもほとんどないはず――」
学術的・社会的な価値がどれほど大きくても、出版ビジネスとしては「割に合わない仕事」であるという矛盾を、小学館という会社がどのように考えるか。それが大野さんの最初の偽らざる思いであったのだ。
だが、前回すでに描いた通り、第三版の企画は思いがけない方向に転がり始める。辞書編集を行う「kotoba」を設立した飯田さんの存在を背景に、KADOKAWAから転職してきた坂倉さんの書いた企画書の実現の可能性が高まっていったからである。
「ただ、そのときになってもまだ、私は坂倉さんに任せて、『日国』は“お手伝い”をするくらいのつもりだったんですよ。坂倉さんが企画書を書いた辞典ですし、自分で企画書を書いた本を編集したいという思いもありましたから」
しかし、坂倉さんが社内の上層部にプレゼンを重ね、小学館の役員たちからのゴーサインも出たことで、辞書編集部の中堅編集者である大野さんの立場は知らぬ間に大きく変わっていた。そして、ある日、飯田さんから彼女ははっきりとこう告げられたのだった。
「編集長になってほしい」
言葉は柔らかかったが、有無を言わさない雰囲気に気圧され、大野さんは「観念した」と今では笑う。
「正直、『え、私ですか?』とは思いました。だって私は、『日国』をやりたいと積極的に手を挙げたわけでもない。でも、『日国』の改訂にかかる時間の長さを考えれば、『いまこの部署で十年後も会社にいる可能性が高い人間は誰か』となったとき、まずは私しかいなかったのでしょうね」
だが、そう謙遜するように語るときの大野さんは、どこか楽しげでもあった。
「そのときに、はっきり思ったんです」
と、彼女は言った。
「ああ、これはもう逃げられない仕事になったな、って。辞書の世界にいれば、『日国』が特別な辞典だということは誰もが分かっています。研究者の人たちが真っ先に引く素晴らしい辞典。だから、『いつかは改訂しなきゃいけない辞典』ということは知っていました。まァ、それがどうして『私』なんだろう、という思いは今でもありますけどね」
では、『日国』の改訂作業のリーダーとなった当初、彼女はまずはどのような視点によってこの仕事を進めることにしたのか。
(つづく)
概要
「これは戦後の日本文化を代表する偉業の一つ」…丸谷才一が、そう激賞した日本最大の国語辞典がある。収録語数約50万を誇る日本語の基本台帳であり、「古事記」「万葉集」以来あらゆる文献を渉猟して集めた言葉の実例(用例)約100万とも号する『日本国語大辞典』は、初版刊行後約半世紀を経て、いま新しい姿に生まれ変わろうとしている。“日国”を生んだ辞書編纂者一族の松井家の物語、そして新版改訂に関わる編集委員、編集者の証言を集めた大宅賞受賞作家・稲泉連によるルポルタージュ、連載開始。
プロフィール
稲泉連
いないずみ・れん/1979年、東京都生まれ。早稲田大学第二文学部卒業。2005年に『ぼくもいくさに征くのだけれど 竹内浩三の詩と死』で第36回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。主な著書に『復興の書店』『「本をつくる」という仕事』『サーカスの子』など。最新作『パラリンピックと日本人』が2024年度ミズノスポーツライター賞 最優秀賞を受賞。
コラム記事一覧
-
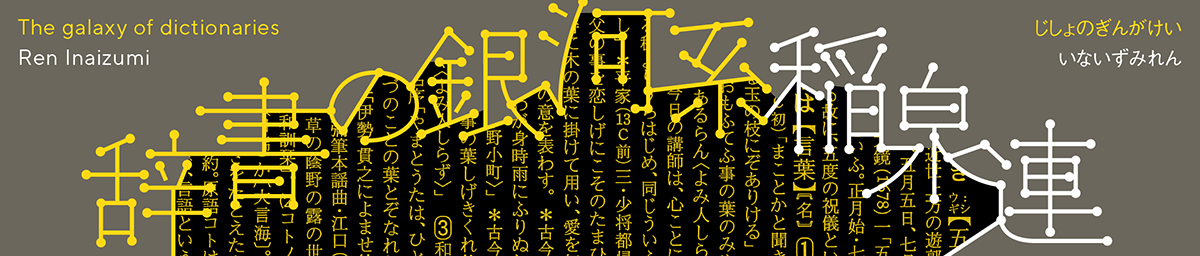
第2回 後編
(第2回中編からつづく) 総合出版社はコミックやライトノベル、はては出版を飛びだしてアニメやゲームなど収益源の多角化を加速させてきたが、インターネットの発展も相まって、赤字かそれに近い辞書の出版を続ける経営的な理由は薄まってきたと言わざるを得ない。 坂倉さんが『新字源』の改訂を行っていた際も、2015年頃には予算の今後に課題が生じ、定年退職を迎える先輩がいよいよ会社を去り始めると、補充のない辞…
コラムを読む -
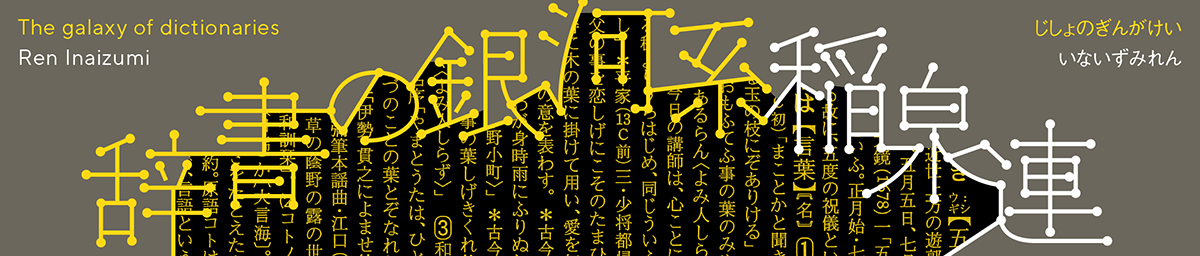
第2回 中編
(第2回前編からつづく) 坂倉さんは大学で東洋哲学を学んだ後、KADOKAWAグループとなるメディアワークスに就職した。もともと辞書編集に縁があったわけではなく、同社では雑誌の編集に携わったという。そんなとき、グループ内での人事交流制度の募集があり、興味を抱いたのが角川学芸出版の辞書編集部だった。学生時代に『新字源』をよく使っていたため、最初は「辞書作りをするというのも面白いかもしれない」と軽い…
コラムを読む -
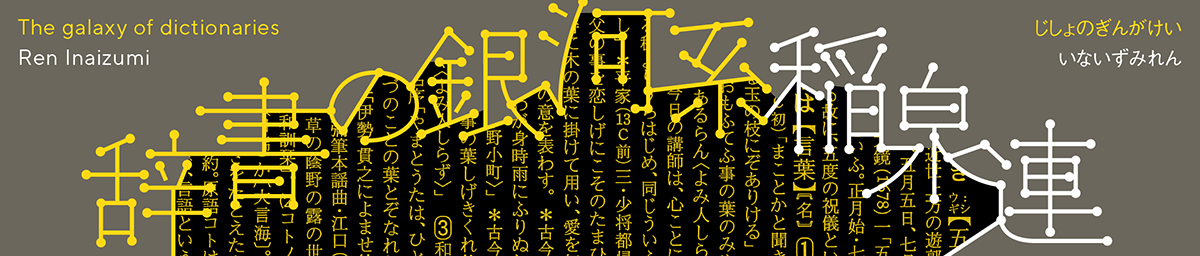
第2回 前編
〈〈 第1回 昨年の7月25日、2025年度の主だった出版事業を発表する小学館の「新企画発表会」が、同社の講堂で行われた。 その日、9つの企画が社長の相賀信宏氏から発表されたなか、ひときわ注目を集めたのが『日本国語大辞典 第三版』の制作決定の報告だった。小説やコミックなど、他の企画がこの一年の間に刊行される予定であったのに対し、「8年後」という「日国」の完成までの歳月の長さが異彩を放っていたか…
コラムを読む -
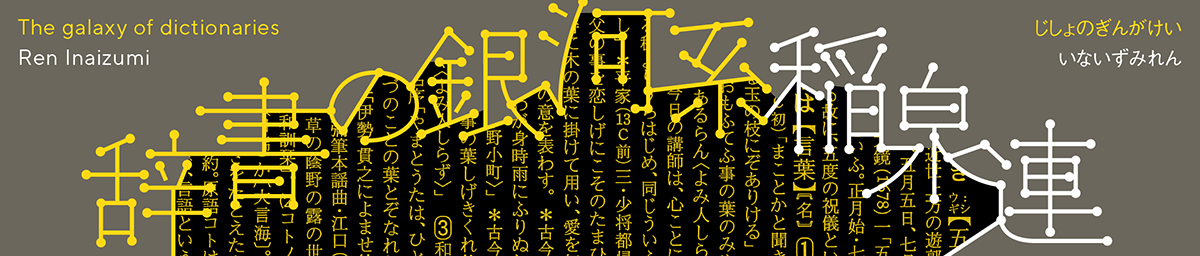
第1回 後編
(第1回 前編からつづく) ――雨に濡れたケヤキや銀杏の木の葉が、ときおり吹く風にざわざわと音を立てている。 飯田さんが引き連れてきた4人の編集者が一人ひとり、墓石の前で手を合わせていく。辞書編集部で『日国』の編集長を務める大野美和さん、KADOKAWAで『新字源』の編集を担当し、一年前に小学館に転職した坂倉基さん、同じく三省堂の辞書編集部の主力編集者だった荻野真友子さん、そして、「kotoba…
コラムを読む -
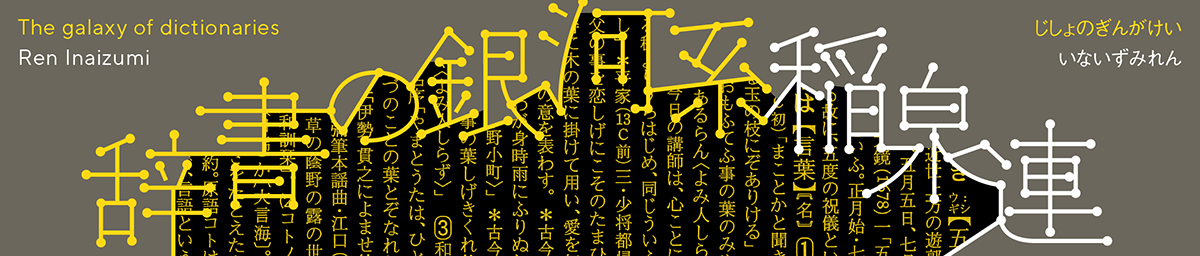
第1回 前編
昨年3月某日、朝から雨が降り続ける肌寒い日のことだった。雑司ヶ谷霊園に約束の時間よりも早く到着した私は、誰もいない墓地をしばらく一人で歩いた。 南池袋の住宅街に広がる雑司ヶ谷霊園は、夏目漱石や小泉八雲、永井荷風、泉鏡花やサトウハチローといった文学者の墓が多いことでも知られる。すぐ近くに池袋の街の喧騒があるのが噓のように静かな場所である。 地下鉄の駅を出た時よりも雨足は強くなり、傘から滴り落ち…
コラムを読む