第2回 前編
昨年の7月25日、2025年度の主だった出版事業を発表する小学館の「新企画発表会」が、同社の講堂で行われた。
その日、9つの企画が社長の相賀信宏氏から発表されたなか、ひときわ注目を集めたのが『日本国語大辞典 第三版』の制作決定の報告だった。小説やコミックなど、他の企画がこの一年の間に刊行される予定であったのに対し、「8年後」という「日国」の完成までの歳月の長さが異彩を放っていたからだ。
相賀社長が「日国」第三版の制作の決定を伝えたとき、別会場でモニターを見ていた人々から、歓声とともに大きな拍手が起こった。集まっていたのはこれから「日国」の編集を担う編集者たち、編集委員を率いる日本語学者・近藤泰弘氏、そして、社外の辞書関係者の面々――。第三版の制作を待ちわびていた彼らにとって、2024年の7月25日はそうして記念すべき日となったのだった。
この新企画発表会の際、第三版をデジタル版で公開し、段階的にバージョンアップしていくことを話した一人の編集者がいた。坂倉基さん――小学館の辞書編集部の主力メンバーとして、第三版の編集に力を発揮することが期待される一人だ。
実はこの坂倉さん、第三版制作の「企画書」を書いた編集者なのである。
「日国のプロジェクトが始まったのは、2023年の秋に『例解学習国語辞典』の改訂版を刊行し、次の仕事をどうしようかと考えていたときのことでした」
と、彼は経緯を振り返る。
「企画の大きさとはそぐわないくらい、最初は気軽なやり取りだったんです。上長の飯田さんと話をしていたとき、『日国をやりたいです』とそれとなく言ったところ、『じゃあ、企画書を出して』と。今から思えば、私が企画書を書いたからと言って、このような大事業が始まるとは考え難いので、もともと小学館の中でも日国の改訂が意識されていたのでしょう。辞書は改訂しないと死んでしまうものです。そして、改訂するためには誰かが企画を出さないといけない。そこに私が出した企画書があったのだと思います」
坂倉さんは第三版の企画書を作る際、この大辞典の惹句として「日本で唯一無二」という言葉を使った。
小学館の辞書を通して「日本の知的基盤」に貢献すること、改訂の意義、そして、スケジュールや予算の見通し、次なる改訂では新たに編集支援システムを作り、編集作業の時点から辞典のデジタル化を進めること……。そうした要素を盛り込んだ企画書は36頁に及んだ。
「それと同時に強調したのが、『日国』が大事にしてきた哲学を変えない、という姿勢でした。何より守らなければならないのは、松井簡治から脈々と続いてきた『日国』の用例主義であるからです。私はこう考えています。例えば、僕らが一つの言葉を同じ意味としてやり取りできるのは、その言葉が辞書に書いてあるから。そして、『日国』にはそのさらにもう一段先に、『過去にこういうふうに使われていた』というエビデンスを示し、私たちの言葉でのコミュニケーションにおける約束を補強する役割がある。それこそが『日国』の唯一無二の特徴であり、『日国』らしさだという点を企画書にはしっかりと書き込んだつもりです」
この連載の第1回でも書いたように、『日本国語大辞典』は国語国文学者の松井簡治が私費を投じて編纂した『大日本国語辞典』に始まり、息子の松井驥、孫の松井栄一と受け継がれてきた仕事だ。しかし、前回の改訂時には編集の中心を担った松井栄一はすでにおらず、今回の改訂では「家業」として守られてきたともいえるその精神を、いかに辞書編集部のメンバーによって継承していくかが問われる――と坂倉さんは語る。
では、松井家の人々が「用例主義」にこだわった理由とは何か。それは日本の文学や芸術、歴史をつむいできた先人たちが「何を書いてきたのか」を提示することが、自分たちのアイデンティティと直結する仕事であると信じたからではなかったか。坂倉さんは企画書を作りながら、そのような思いを日に日に強くしていったそうだ。
「人類というのは、誰もが先人たちが作ってきた文化を受け継いできました。文学や歴史を学ぶことの大きな意味が、そこにあると私は思っています。そして、文学や歴史を学ぶという営みとは、人類の知的営為の一つである何らかの文献やテキストが、なぜ書かれたのか、何が書かれているのか、どう取り扱われて来たのかを丹念に調べることでしょう。
かつて『日国』のような辞書がなかった時代、当時の国語国文学者はまず言葉の索引を作るところから研究を始めました。その索引を公と共有するために辞書を作ろうと考えたところに、松井簡治や松井栄一の偉大さがあった。第三版では僕らがそのポリシーをしっかりと受け継いでいきたいと思っています」
ところで話を聞いてみると、坂倉さんは数年前までKADOKAWAの編集者をしており、所沢市にある同社の図書館事業も担当していたという。いわば、小学館辞書編集部では新顔に当たる彼が、なぜ、「日国」の企画書を書くという大役を担ったのだろうか。そこには一人の「編集者」が仕事を通して、「辞書編集者」となっていったキャリアの変遷がある。
(第2回中編につづく)

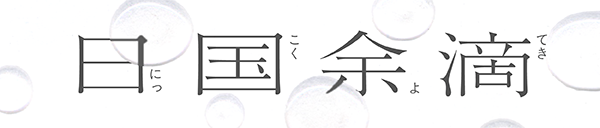 日国余滴
日国余滴 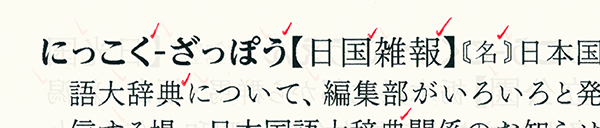 日国雑報
日国雑報 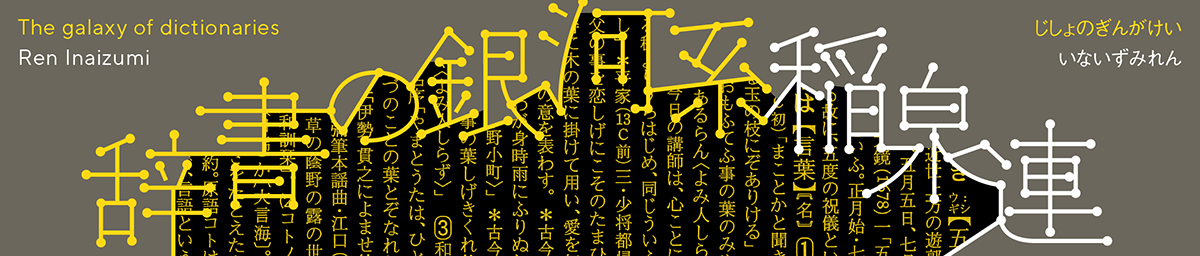 辞書の銀河系
辞書の銀河系 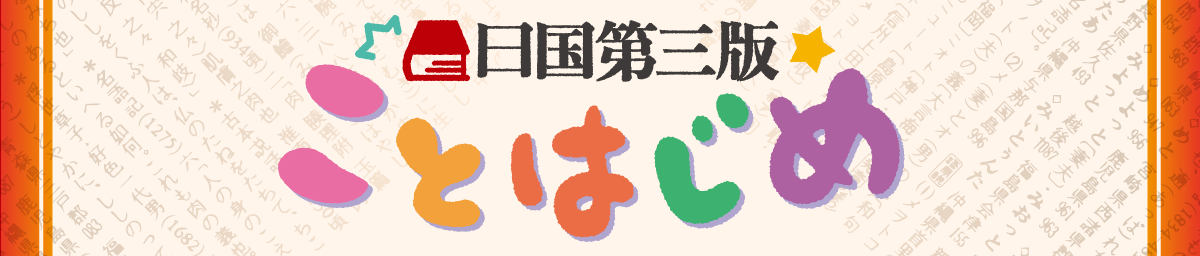 日国第三版 ことはじめ
日国第三版 ことはじめ  不思議の国ニッポン!!
不思議の国ニッポン!! 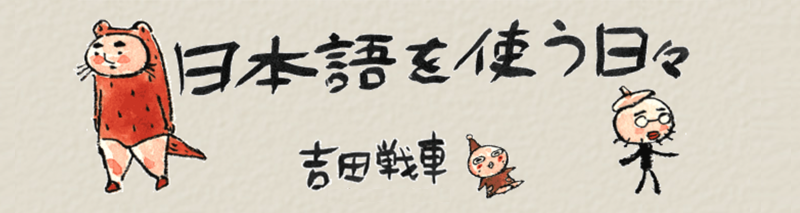 日本語を使う日々
日本語を使う日々  日本語マナーの歳時記
日本語マナーの歳時記  女子大生でも気づかない方言
女子大生でも気づかない方言  共通語な方言
共通語な方言  山根一眞の調べもの極意伝
山根一眞の調べもの極意伝 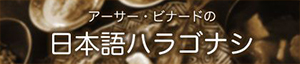 日本語ハラゴナシ
日本語ハラゴナシ 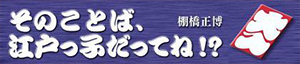 そのことば、江戸っ子だってね!?
そのことば、江戸っ子だってね!?