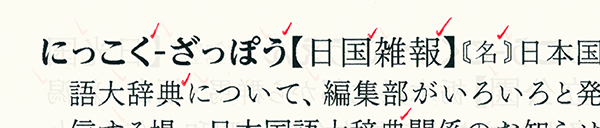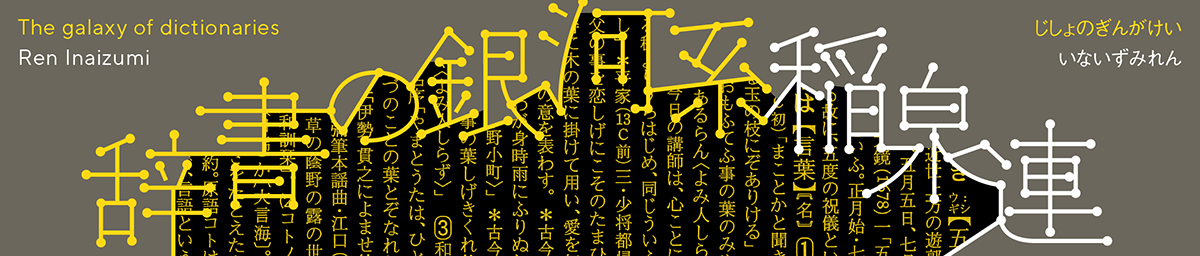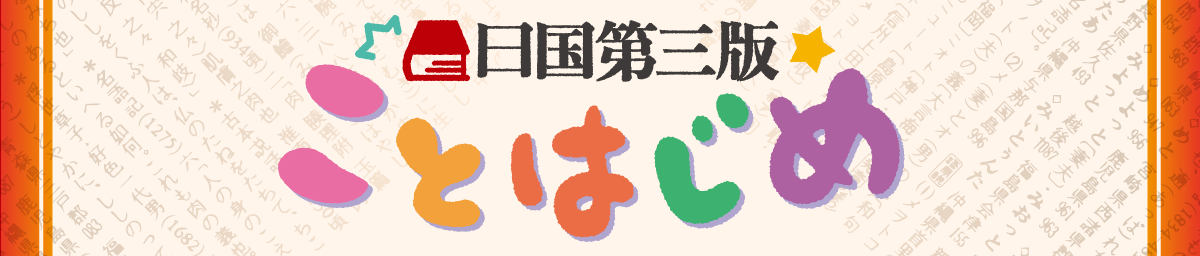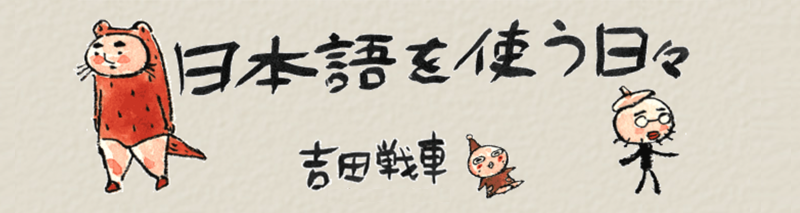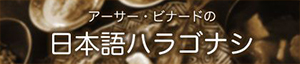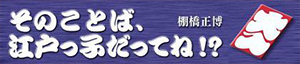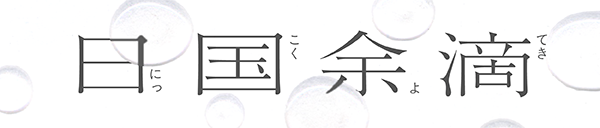
日国余滴
木簡が教えてくれるいにしえの価値/鯛、鰯、鯖、鮫、鰹、鮑
渡辺 晃宏
木簡は食品名の宝庫といってよい。中でも顕著なのはさまざまな海産物である。山の幸よりも海の幸が豊富であるのは、それらの多くが海に面しない盆地にある大和の王権のもとに、各地から届けられた貢進物の荷札であることと無縁ではないだろう。
イワシは伊和志であり鰯でもある
木簡に見える海産物の表記には、今と全く同じ鰯、鯛、鯖などの漢字も登場する。しかし、そればかりではない。これらを、伊和志、多比、佐波などのように、万葉がなで表記した事例がめだつのである。しかも、漢字表記と万葉がな表記のどちらが優勢かというと、不思議なことに海産物の品目ごとに違いがあることがわかる。
例えばイワシは、万葉がなで「伊和志」「伊委志」「伊委之」と表記する事例が多い。「鰯」の事例が見え始めるのは8世紀末からだが、8世紀初めの長屋王家木簡にも僅か1点だが「鰯」の事例があるから、「鰯」は出現自体が降(くだ)るわけではない。サメの場合はさらに顕著で、8世紀までのサメは「佐米」と万葉がな表記する例しか知られず、「鮫」の漢字表記は一つもないのである。もっとも、このサメの場合も、「鮫」の漢字が知られていなかったわけではないことは、735、736年頃を中心とする二条大路木簡の中のいわゆる字書木簡に、鮫〈佐米〉とあることから明らかである。
これと正反対なのがサバで、8世紀初めの長屋王家木簡に「佐波」が1点知られるが、ほとんどが「鯖」と表記されている。同様の傾向を示すものにアユがあり、藤原宮跡の木簡に「阿由」が知られるものの、多くは「鮎」で、「年魚」という特殊な表記も多い。
これらの中間にあるのが、タイである。「鯛」と漢字で表記する事例がある一方で、「多比」の万葉がな表記の事例もめだつ。似た傾向を示すものにはイカがある。漢字表記の「烏賊」が広く用いられる一方、万葉がなによる「伊加」と表記する事例も多い。
このように、海産物の名称についての漢字表記と万葉がな表記のバランスが、品目によって異なる傾向を示すのである。これが時期差でないことは、8世紀前半には少なくとの多くの海産物の漢字表記が知られるわけであるから間違いない。万葉がな表記が用いられた理由自体については、音声の世界が卓越していた古くからの伝統に根差すところの王権への貢進物だからということで説明されることが多い。
カツオとアワビの謎
ところが、木簡に頻繁に登場する海産物に、万葉がな表記の事例が全く見られない品目が実は存在する。それはカツオとアワビである。カツオは「堅魚」(古代に遡る「鰹」の事例はない)、アワビは、「鮑」または「鰒」(稀に「蝮」も)の表記に統一されているのである。後者の表記は併用されたが、安房国(上総国に統合されていた時期も含む)のアワビは必ず「鰒」と表記しており、国による表記の個性も顕著である。
カツオもアワビも、神への献げ物、すなわち神饌(しんせん)としても重視された物品であるのに、万葉がな表記の事例が知られていないのはなぜか。前述のように、万葉がな表記が古い伝統の証であるならば、カツオやアワビの貢進の成立は意外と新しいということなのであろうか。いや、そうではあるまい。むしろ古くからある重要な貢進物であるからこそ、表記の統一が図られたと解すべきなのではなかろうか。
7世紀後半になって唐に倣った律令国家建設に向けて租税制度が整えられ、荷札を付した貢進が始められたとき、貢進物を漢字でどう表記するかが検討された。日本近海の海産物のほとんどは、それを示す漢字は存在しなかったはずである。そのため、
(1)類似した海産物の表記を代用する…鯛・鰒など
(2)別の海産物を指すことを承知の上でイメージに合う漢字を充てる…鮎・鯖など
(3)イメージに合う漢字(国字)を作る…鰯など
(4)イメージに合う熟語を作る…堅魚・年魚など
といったさまざまな方法で充てる漢字を工夫したとみられる。そして、特に大事な貢進物には表記の統一の徹底が図られる一方、それほどでもないものは万葉がな表記が併存し続けたということなのであろう。
表記の決定自体は中央政府が行った(令の規定など)わけだが、その表記が早くに定着するものと、定着が遅れるものがある。そこには国ごとの地域差も加わったことであろう。中には万葉がな表記を墨守する地域も出てくる。前述の「佐米」は三河湾三島の特徴的な書式の贄貢進にのみ見られる特異な品目のかつ個性的な表記である。しかもその淵源は意外と新しく、702年の持統太上天皇の参河行幸にあると目されている。
漢字表記と万葉がな表記の問題は、木簡というナマの資料があればこそ考察が可能になった。まだ結論を充分には見通せていないが、その一端を述べてみた。

イラスト/大崎メグミ https://omegumi.jp/
◎プロフィール
渡辺晃宏
わたなべ・あきひろ/1960年東京都生。奈良大学文学部教授、奈良文化財研究所客員研究員。木簡学会副会長を務める。平城宮・京跡の発掘調査と木簡の整理・解読に31年間従事したあと、2020年より現職。専門は日本古代史。
概要
よ‐てき 【余滴】
(1) 筆の先や硯(すずり)などに残った墨のしずく。
(2) 雨の後のしたたり。
(3) ある作業の副産物。「研究余滴」
(『現代国語例解辞典 第五版』より)
『日本国語大辞典』の改訂作業のなかでの発見や、辞書には記述されにくいこと、辞書からこぼれ落ちてしまうことなどを不定期で掲載します。
プロフィール
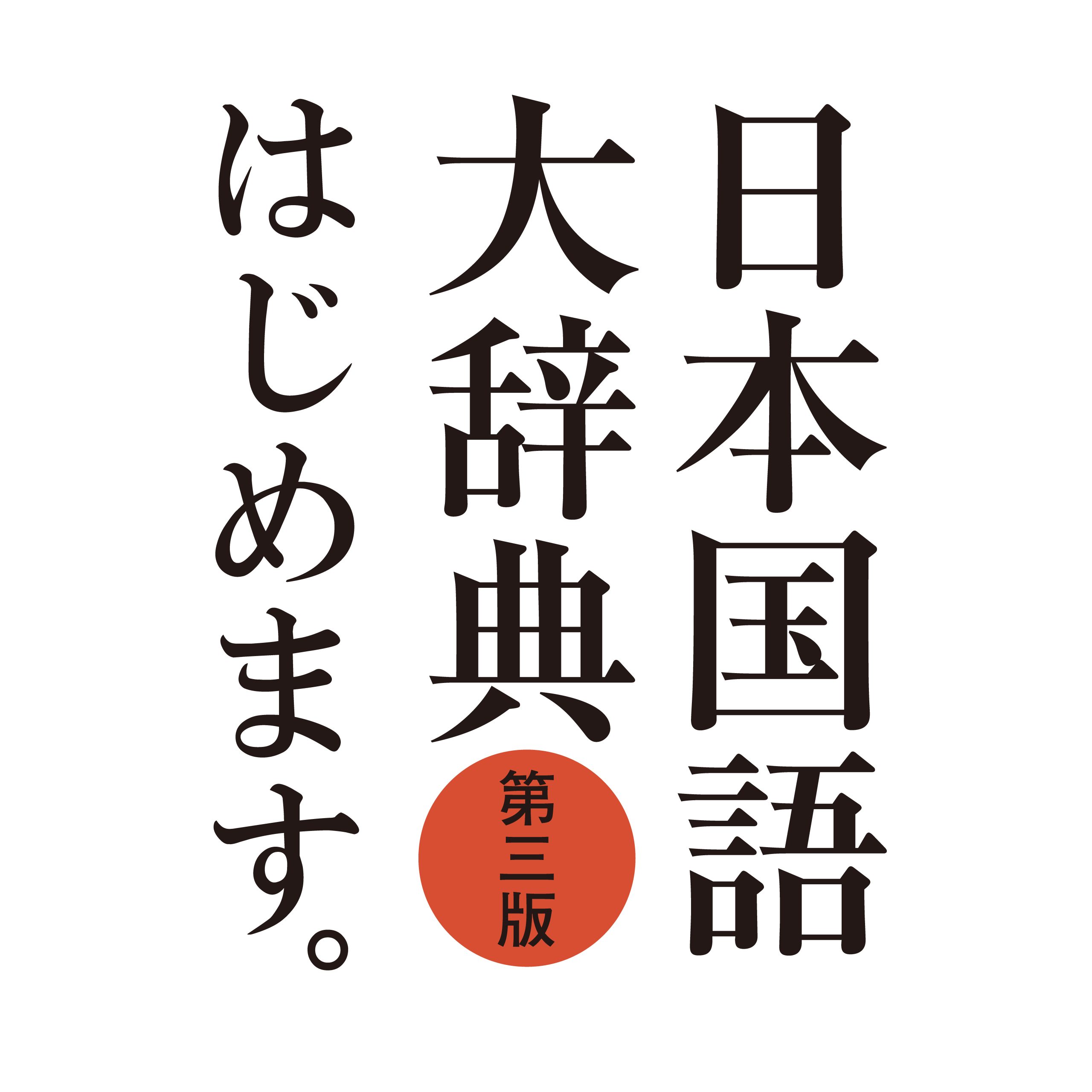
『日国』編集部
この連載は『日本国語大辞典 第三版』の編集に携わっている方からの寄稿記事です。各記事にプロフィールを添えています。
コラム記事一覧
-
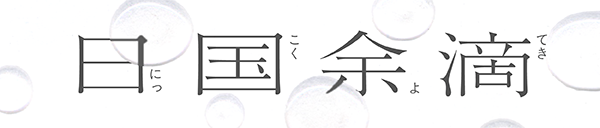
アクセントを見える化する
加藤 大鶴 学生から『鬼滅の刃』に出てくる「猗窩座(あかざ)」というキャラクターのアクセントが人によって違うということが話題になっていると聞いてから、アクセントを扱う授業では「つかみ」として用いることが幾度かあった。「みなさん、あかざ(頭高型・①型)とあかざ(平板型・⓪型)、どちらのアクセントですか?」というやりとりは、それなりに学生を引きつける話題であったし、言葉を扱う教員ならすぐにイメージ…
コラムを読む -
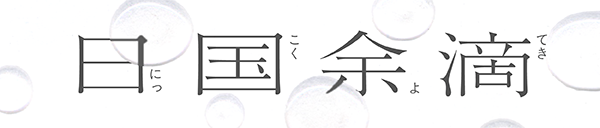
明治以降に増えた新漢語「共_」をめぐる疑問
田中 牧郎 「新漢語」と呼ばれる「新しい漢語」 日本語の語彙は明治時代から突然増える。その多くは熟語(漢語)だ。明治以降に登場するものは、江戸時代より前の漢語と区別して「新漢語」と呼ばれることがある。ある漢字に注目すると、江戸時代以前にも多く使われていたが、新漢語で使われる機会がぐっと増えたものがある。 それはどのような字で、なにが理由なのか、ひもといていきたい。 「共(キョウ)」は明治…
コラムを読む -
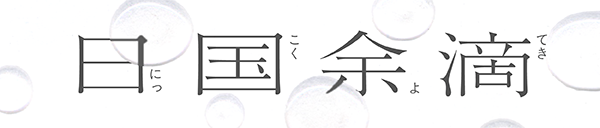
逆の意味―訓点資料の世界―
山本 真吾 今からもう二十年くらい前になるでしょうか。勤務先の大学のキャンパスで、あるとき、「やばい、やばい」と騒ぐ学生たちの声が聞こえてきました。「授業に遅れそうなのかな」「ハチでも出たのかな」と様子をうかがってみたのですが、本人たちにはまったく緊迫した感じはなく、笑顔ではしゃいでいます。よく見ると手には大学近くのお店で売っている話題のスイーツをもち、それをほおばりながら「やばい」という言…
コラムを読む -
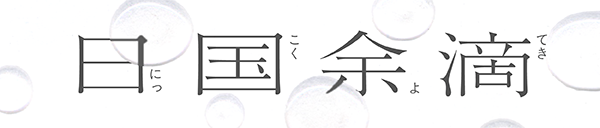
「へ」と「に」の微妙な関係
前田 直子 海外ではどのくらいの人が日本語を学んでいるのだろうか。外国語学習者数の指標は種々あるが、一例として外国語学習アプリDuolingoの利用者データ(2024年)を見てみよう。 1位 英語 2位 スペイン語 3位 フランス語 4位 ドイツ語 5位 日本語 6位 イタリア語 7位 韓国語 8位 中国語 9位 ポルトガル語 10位 ヒンディー語 ――「2024年版 Duolingo La…
コラムを読む -
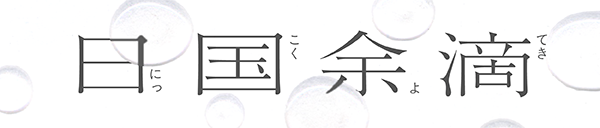
関西方言の「イキル」と若者語の「イキる」
日高 水穂 関西方言に「イキル」という語がある。「アイツ ナニ イキットンネン(あいつ何イキッテルんだ)」のように使う。鼻につく、癇(かん)に障るものとして、関西人はことさらに「イキリ」に敏感なようなのだが、関西ネイティブではない私には、いまひとつピンとこないでいた。 牧村史陽編『大阪方言事典』(杉本書店、1955年)には、「勢が盛んになる。きほひ立つ。元気づく。」とあるのだが、どうもニュ…
コラムを読む -
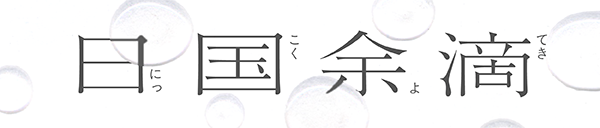
「中抜け」の語の謎
近藤 泰弘 「あげつらう」という語がある。「日国」によると「物事の善悪、理非などを議論する。物事の是非をただす。また、ささいな非などをことさらに取り立てて言う」とある。ちょっと文語的な古風な表現ではあるが、特に最後の「ことさらに言う」という意味では現在でも普通に使われる語であると言っていい。試みにX(旧twitter)で検索してみても、「ことさらにあげつらう」「つまらんことをあげつらう」「あ…
コラムを読む -
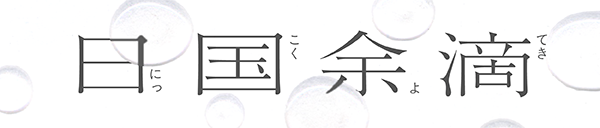
「す」(【鬆・巣】)についての歴史的・地理的考察
金水 敏 この語について興味を抱いたのは、私が最近好んで視聴しているYouTubeチャンネル「野食ハンター茸本朗(たけもとあきら)ch」に上がっていた、「ワケありで意味シンなひどい名前のイソギンチャクをペロリといただく」というタイトルの動画【*1】に出会ったことがきっかけであった。 このチャンネルは、茸本朗さんという方が、野草、野鳥、流通の少ない魚介類等をハントしてきては、自分で調理してお…
コラムを読む