第2回 中編
(第2回前編からつづく)
坂倉さんは大学で東洋哲学を学んだ後、KADOKAWAグループとなるメディアワークスに就職した。もともと辞書編集に縁があったわけではなく、同社では雑誌の編集に携わったという。そんなとき、グループ内での人事交流制度の募集があり、興味を抱いたのが角川学芸出版の辞書編集部だった。学生時代に『新字源』をよく使っていたため、最初は「辞書作りをするというのも面白いかもしれない」と軽い気持ちだったという。
角川書店の『新字源』は、三省堂の『漢辞海』や学研の『漢字源』などと並ぶ日本を代表する漢和辞典で、中国の古典を読むための単語や漢字の意味が説明されていることで知られる。当時、同社ではこの『新字源』の改訂作業が進められており、坂倉さんはその一員として辞書編集部に異動することになったのだ。
「『数年ぶりの新人だ』ということで、OBを含めたベテランの方々がすごく喜んでくださったのが印象的でした。そして、僕自身も『新字源』の編集部にいちばん下っ端として入ることになったんです」
坂倉さんがまず戸惑ったのは、辞書編集部の「時間の流れ」だった。一つの作業の締め切りが三か月後や半年後のこともあり、「明日の入稿」や「今日中の校了」に追われていた雑誌の編集部とは全く異なる世界がそこにはあった。
そして、重ねて印象的だったのが、異動した初日に上司から「これは今日から君のだから」と『新字源』を渡されたことだ。
「まずはこの辞書の常用漢字の箇所に、すべてに付箋を立てなさい」
『新字源』を最初から読み、常用漢字を目視で確認しては手を動かす。坂倉さんはその作業を来る日も来る日も繰り返すことになった。
「それは辞書編集の基礎であると同時に、『常用漢字とは何か』ということを肌で理解させるための教育でもあったのでしょう。けれど、そのときの僕には、終わりの見えない作業に感じられたものです。そして、常用漢字が終わると、次は人名用漢字に付箋を貼れ、と。人名用漢字は数百個ですが、実際に一日で何字進められるのか、というペースが分からない。いま思えば、それが『辞書編集』という仕事のペースをつかむための、最初の研修期間だったんですね」
一冊の辞書づくりはときに数年単位で一つの仕事に取り組むものとなる。「来月の校了」ではなく、「三年後の完成」をどのようにイメージしながら編集作業を進めていくか。坂倉さんは辞書編集部に異動した際、まずはその感覚を頭に叩き込まれていったわけである。
「そんな風に辞書編集という仕事の時間の流れに圧倒されながら、僕の最初の仕事は『新字源』の手伝いから始まりました。ほかにも、『江戸時代語辞典』を任されたり、『皇室辞典』の編集に入ったりとさまざまな辞書に関わりました。古い辞書の電子化作業にも携わるようにもなりました。そうして少しずつ、辞書の世界の『時間の流れ』に、僕自身の身体も馴染んでいったように思います」
その後、長年にわたって『新字源』の編集に携わるなかで、坂倉さんはその改訂作業の全体を指揮する立場になっていく。『新字源』の改訂が進められるうちに、先輩社員の何人かが定年を迎えていったためだ。
「そのなかで知るようになった辞書編集の醍醐味にも、私は『唯一無二』という言葉を使いたいです」
と、坂倉さんは笑う。
「例えば、編集者として一冊の単行本を作ったとして、もちろん最高の一冊を目指すわけですが、ほとんどの場合は類書があります。造作や中身が似たものや、より詳しい内容にしたものを他の人が作ってしまうかもしれない。たとえば中国古典の『孫子』に関する本はたくさんありますが、子どもや初学者向けのやさしいものから、原著に詳しい注釈のついたもの、解説書や研究書まで、様々な種類と内容の本がありますよね。だから、私が作った『孫子』に関係する本に載っていないことも、他に詳しい内容のものを読めば分かるわけです」
でも――と彼は言う。
「辞書ってそれより後ろがもうないんです。辞書に載っていないことは、世の中になかったことにされてしまう可能性がある。それに、多くの人はたくさんの辞書を持っていません。目の前の辞書に載っていなかったときに、次の辞書を引いてくれるかどうか」
それから、もう一つ辞書編集者として重要なのは、辞書の持つ「規範性」への理解だと彼は考えている。
「規範といっても正しさのことではありません。辞書の役割というのは、結局のところコミュニケーションをいかに円滑にするか、という話ですよね。たとえば私が何かを考えていて、それを誰かに伝えようとする。そのとき、私が選んだ言葉の意味と、それを受け取った相手の理解が一致していなければ、コミュニケーションは上手くいきません。ところが、私が『こういう意味で使っている』と思っていても、相手が同じ意味で受け取っているかはわからないわけです。
それをつなぐのが辞書だと私は捉えています。『辞書的にはこうだよね』という言い方があるように、辞書に載っていれば、人はお互いに共通の理解で言葉を使っていることが確認できる。そんなふうに、辞書は社会の根っこにあるコミュニケーションを支える仕組みでもあると信じているからこそ、この仕事にやりがいを感じられるんですよ」
言葉を扱う辞書の仕事って――と坂倉さんは言うと、真っすぐに私の目を見て続けた。
「すごく奥深くて、他には代えがたい魅力がある。KADOKAWAで辞書を作るようになって、そうした唯一無二の性質が辞書編集者という仕事の醍醐味であると私は思うようになっていったんですね」
しかし、一方でKADOKAWAの辞書編集部での日々は、坂倉さんにとって「辞書」という出版の分野が縮小していく時代の流れの中で、現状をいかに維持するかに苦心しながら仕事をした時間でもあった。
(第2回後編につづく)

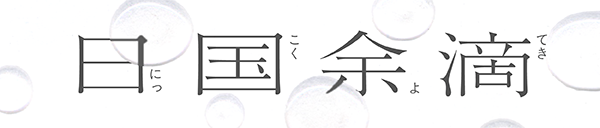 日国余滴
日国余滴 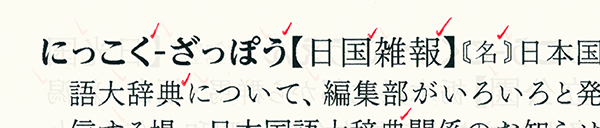 日国雑報
日国雑報 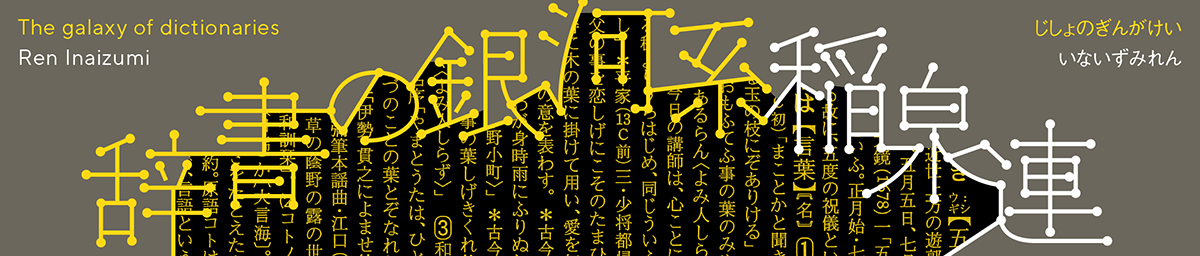 辞書の銀河系
辞書の銀河系 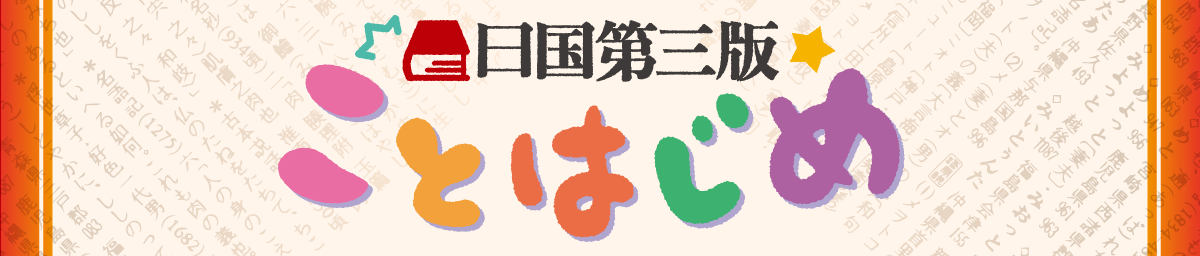 日国第三版 ことはじめ
日国第三版 ことはじめ  不思議の国ニッポン!!
不思議の国ニッポン!! 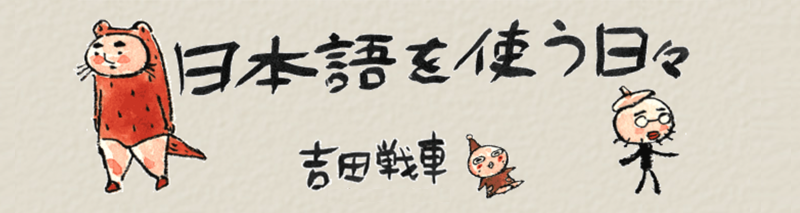 日本語を使う日々
日本語を使う日々  日本語マナーの歳時記
日本語マナーの歳時記  女子大生でも気づかない方言
女子大生でも気づかない方言  共通語な方言
共通語な方言  山根一眞の調べもの極意伝
山根一眞の調べもの極意伝 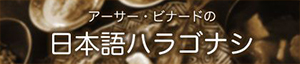 日本語ハラゴナシ
日本語ハラゴナシ 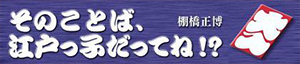 そのことば、江戸っ子だってね!?
そのことば、江戸っ子だってね!?